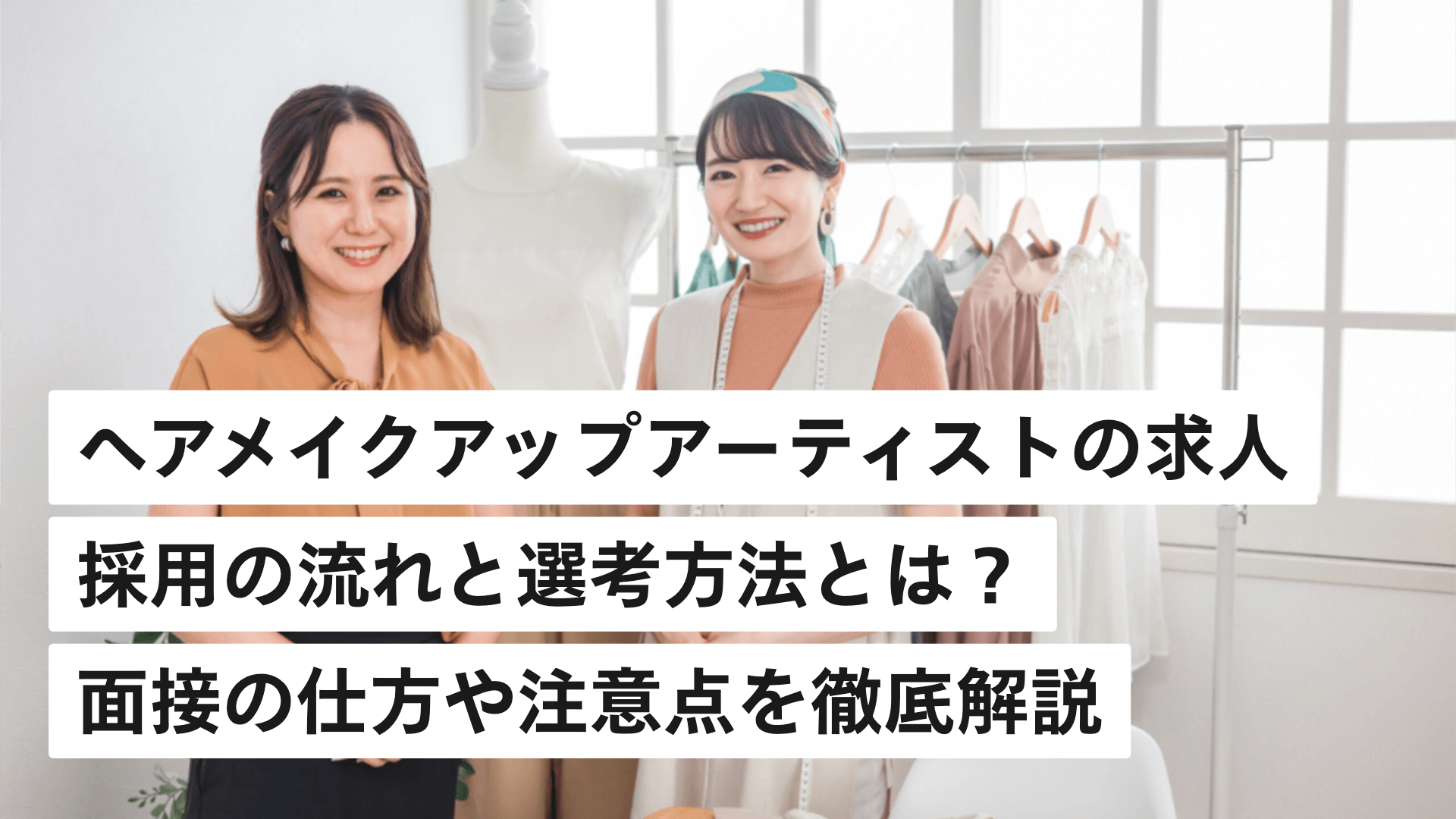
ヘアメイクアップアーティスト採用の流れと選考方法とは?面接の仕方や注意点を徹底解説
採用活動は、応募者についての限られた情報から、自社にふさわしい人を見極める作業となります。
特にヘアメイクの現場は、様々な人々と関わり合いながら仕事をするため、面接でコミュニケーション力を確認できると安心です。そのためには、スムーズかつ適正な選考をするために事前準備が重要となります。
とはいえ、いざ採用活動をしようとするとき、実際の流れがわかならかったり、面接で何を質問すべきなのかを悩む人事担当者も多いのではないでしょうか。
この記事では、ヘアメイクアップアーティストを採用する流れと選考方法、面接の仕方や採用・不採用の通知について詳しく解説します。これから求人募集をする際に、ぜひご活用ください。
優秀な人材と出会うための求人方法とは
優秀なヘアメイクアップアーティスト(以下、ヘアメイクさんという)を採用するためには、適切な求人方法と選考方法が重要です。
採用活動は、まず求める人材像を明確にし、適切な求人方法と選考方法を選定したうえで、募集タイミングを工夫することで、適材の採用が可能になります。
選考に大きくかかわる求人方法と選考方法を詳しくみていきましょう。
求人方法
様々な求人方法と求人媒体の中から、自社の求めている人材と親和性の高い方法で募集をかけましょう。以下は、一般的な求人媒体の一例です。
【一般的な求人媒体一例】
| 求人媒体 | 出会える人材・求める人材・媒体の特徴など |
| 新卒専門求人サイト | 新卒生(未経験可)を希望する場合 |
| 既卒・中途専門転職サイト | 転職希望者、経験者を希望する場合 |
| 専門職の求人サイト | 専門の資格を保持していたり、技術者を求める場合 |
| 専門学校へ求人案内 | 新卒生(未経験可)を求める場合 学校からの推薦書が就くこともある |
| リファラル採用 | 従業員や取引先などからの即戦力の紹介(自社の基準とマッチする人材を求める場合) |
| ハローワーク | 公的な求人方法(既卒・新卒関係なく募集できる) |
| 自社ホームページ | 縁故採用も含まれる |
| 求人媒体 | 出会える人材・求める人材・媒体の特徴など |
以下の記事では、ヘアメイクアップアーティストを探す求人媒体の種類と選定方法について解説しています。
選考方法
一般的な求人媒体を利用する場合、Webの履歴書などを含む書類選考の後に面接選考の流れとなります。
求人を募集することが決定したら、企業は「どんなヘアメイクさんを求めているのか」を明確化します。そのうえで求人媒体の求人申込書に記入し、募集要項を作成しましょう。その後、求人申込書を求人媒体に提出し、求職者の募集と選考が始まります。
最終的に、応募者の中から採用または不採用を決定し、通知をおこなうのが一連の流れです。
例えば、Indeedやハローワーク、自社サイトなど、利用する媒体によって必要な項目や手続きが異なるため、各媒体にあわせて準備や選考をおこないましょう。
【一般的な採用活動の流れ】
- 求める人材像の明確化
- 企業が求人媒体の求人申込書に記入(募集要項の作成)
- 求人申込書を求人媒体へ提出
- 求職者を募集、選考
- 採用・不採用の決定と通知
採用活動のベースとなる「求める人材の明確化」の重要性は、以下の記事で紹介しています。
書類選考
一次選考は、一般的に書類選考がおこなわれます。
書類選考は、応募者にプロフィール・顔写真・学歴・経歴などを開示してもらうことで、応募者の情報を知ると同時に、自社が求めている条件にマッチしているのかを判断できます。まさに、採用活動の第一関門ともいえるでしょう。
ヘアメイクさんの採用を目的とする場合、過去の作品をまとめた「コンポジット」を添付してもらうと技術力やセンスを判断する参考になります。
また、最近ではSNSで作品を投稿している人も多いため、可能であればSNSアカウントを共有してもらうのもおすすめです。
【応募書類として提出してもらうもの一例】
顔写真付きの履歴書
応募者の雰囲気と学歴を確認する
職務経歴書
応募者の経歴を確認する
志望動機書
入社への熱意や、自社との相性がよいのかを確認する
過去の作品集(コンポジット)
技術力やセンスを確認する
面接について
書類選考を通過した応募者は、面接選考に移行します。
従来より、対面での面接が基本とはされつつも、最近はインターネットの普及によりオンライン面接も増えてきました。
このふたつの方法を組み合わせて、応募開始時の書類提出から、一次もしくは二次面接まではオンライン、最終選考は対面というケースも多くみられます。
選考方法は企業ごとに自由に決定できるものですが、対面とオンラインそれぞれの特性を理解し、適切に活用することが大切です。どちらの面接スタイルにも対応できるよう準備しておくと、より多くのご縁に恵まれるでしょう。
面接時間の目安
面接の回数や時間は企業によって異なりますが、一般的には、一次面接から最終面接まで複数回おこなわれます。人気の企業では、面接回数が多くなることもあるでしょう。
また、一度の面接時間は30分から1時間程度が目安とされていますが、極端に短かったり、長ければよい、というわけではありません。
対面の面接は応募者と直接言葉をかわし、質問などをできる貴重な機会となりますので、できるだけ有効に活用するために、「何分間面接するのか」「その時間内で何を確認するのか」を事前に決めておきましょう。
一次面接
一次面接では、応募者の人柄や考え方を知るための重要なステップです。
書類選考だけではわからない応募者の第一印象・身だしなみ・マナー・話し方などを確認しましょう。
この段階では、応募者の人間性を把握することが目的で、時間をかけて慎重に判断することが求められます。また、企業と応募者が初めて対面する機会となるため、リラックスした雰囲気をつくることも大切です。 長引かないように注意をしつつも、慎重に判断しましょう。
【チェックポイント】
第一印象
自社の雰囲気にあうのか、好印象であるのか
身だしなみ
清潔感はあるのか、自社のヘアメイクアップアーティストとして適正な姿をしているか
マナーや話し方など
接客業に向いているのか
二次面接
二次面接では、一次面接よりも「仕事をしたとき」を想定して質問をします。
例えば、自社の業務に向いているのか、現在働いている社員との相性などを確認してみましょう。
特に、ヘアメイクさんはチームワークが重要な職種であるため、社内ルールや社員との相性があうかどうかを見極めることがポイントとなります。
また、この段階で応募者が会社に求めるものも確認しておきましょう。
例えば、就業時間や評価規定などの働くうえで大切なことを対面で確認したり、応募者からの質問に答えることも大切です。
自社とのフィット感をチェックすることで、応募者が自社の環境に適応できるか、会社全体がチームとしてスムーズに仕事ができるかを見定めます。
【チェックポイント】
- 自社との相性
自社の雰囲気にあうのか、自社のルールを守れるのか - 社員との相性
すでにいる社員とよいチームワークで働けそうか、人間関係のトラブルが起きなさそうか - 応募者が会社に求めるものなどを確認する
自社からだけでなく、応募者にもマッチしているかを確認してもらう
最終面接
最終面接では、質問項目に加えて、具体的な採用条件や入社時期を確認します。
特に、「採用を出した場合、働くことが可能か」「いつから出社できるか」などを質問し、最終段階での応募者の意向を確認しましょう。
また、可能であれば、他に面接を受けている企業があるかどうかを尋ねることも大切です。
最終面接は、企業によって時間の長短は異なりますが、仮に他にも選考が進んでいる場合、他社よりも早く採用通知を出すなどのスピーディーな対応が求められます。最終確認をしたら、迅速な対応で採用を進めましょう。
| 面接の種類 | 面接時間の目安 | 確認すべきこと |
| 対面一次選考 | 約20~30分 | 応募者がどのような人なのかを判断する |
| 対面二次選考 | 約30~1時間 | 自社や社員と相性がよいかを判断する |
| 対面最終面接 | 約15~1時間 | 応募者の働く意志や具体的な入社時期を確認する |
| オンライン面接 | 対面面接に同じ | 対面面接に同じ |
対面面接のポイント
採用面接では、限られた時間内で複数の応募者を評価しなければならない場合もあります。
特に対面での面接は、履歴書やコンポジットなどの資料とともに、確認しておきたいことをまとめた「対面面接の確認リスト」を事前に作成しておくと便利です。
さらに、質問したい項目をまとめた「質問リスト」も別途作成しておくと、面接がスムーズに進行し、聞き漏れもなくなるため、自社にあった人材を効率的に見つけられるでしょう。
まずは、実際の「対面面接の確認リスト」を作るときのポイントをご紹介します。
対面面接の確認リスト
まず、対面面接の確認リストには、応募者の第一印象や身だしなみ・マナー・話し方など、実際に会ってみないとわからない情報をリストアップします。
このリストを使用することで、面接官ごとの評価のブレを防ぎ、一定の共通認識が保たれ、まだ応募者に会えていない社員もどのような人材であるのかをイメージできます。
対面面接の確認リストの作り方と注意
対面面接の確認リストは、対面面接を振り返ったときに、面接や応募者の様子を思い出せるような内容で作成することが大切です。
そのためには、以下のことに気をつけながら記載する内容を考えてみましょう。
求める人材を明確化する
対面面接の確認リストには、「どんなヘアメイクを求めているか」求める人材像を具体的に記載しましょう。
例えば、「明るい人」「笑顔がはつらつとしている人」「声が聞き取りやすい人」など、実際に会ってみないとわからない項目をあげていきます。
評価項目の作成
書き出した項目をグループ分けし、評価項目として明確にします。
グループ分けをおこなうことで、見やすく整理され、面接時の確認がしやすくなります。重複する項目は統合し、評価項目を厳選していきましょう。
評価欄の作成
面接の進行をよりスムーズにするため、そして、応募者の様子を思い出せるような内容にするためには、評価項目に対して「数字評価」と「記述評価」の2種類の欄を作るのがおすすめです。
5段階の数字評価欄を設けることで、面接時に迅速に評価ができ、隣に自由記載のメモ欄を用意しておくことで、特記事項を記録できます。
実際の面接で感じたことを書くことも大切
対面面接の確認リストに頼りすぎると、面接が機械的になり、応募者のよさを見逃す可能性があるので注意が必要です。
このような事態を防ぐために、確認リストは必要事項を厳選し、実際の面接で感じたことを自由に記載できる欄も設けるとよいでしょう。
また、応募者に評価していることが過度に伝わらないように配慮し、自然な雰囲気で面接を進めることも大切です。その中でも、応募者の「希望する店舗」や「出勤できる時間や曜日」などの重要な情報はしっかりとメモしておきましょう。
〈対面面接の確認リストの一例〉
【◯月◯日◯◯時◯◯分対面面接_▢▢ ▢▢さん】
| 確認リスト | 評価 | メモ |
| 身だしなみ | 1・2・3・4・5 | |
| 清潔感があるか | 1・2・3・4・5 | |
| 笑顔で話せるか | 1・2・3・4・5 | |
| 相手の目を見て話せるか | 1・2・3・4・5 | |
| 声の大きさ | 1・2・3・4・5 | |
| 自由項目 | 1・2・3・4・5 |
自由記載用に設けたメモ欄には、「声の大きさは普通より小さいかもしれないが、聞き取りやすい」「優しい話し方で、接客に向いている」や「相手に好感を与える笑顔」など、実際に会ってみて感じたことを書いておくとよいでしょう。
また、この対面面接の確認リストは、オンライン面接にも応用できます。
オンライン面接
先述したとおり、ネット社会の進展やコロナ禍の影響で、以前に比べるとオンライン面接も一般的になりました。
非接触であることはもちろん、企業側は場所の準備が不要で、応募者も面接会場に足を運ぶ必要がないため、双方にとって大きなメリットがあるといえるでしょう。また、最近では、事前に送付した質問に応募者が回答する形式の「録画タイプ」もあります。
オンライン面接で気をつけること
オンライン面接は、顔を見てリアルタイムで対話できるため、対面と大きく変わらない感覚で選考が進められます。ただし、オンラインならではの気をつけなければならないこともありますので、以下の5点に留意しておきましょう。
非言語情報が弱まること
オンライン面接では、対面と比べて非言語情報が伝わりにくくなります。
表情やジェスチャーが見えにくいため、言葉遣いや声のトーンを意識し、質問や感情を明確に伝えることが重要です。画面越しに淡々と話してしまうと、威圧的に感じさせてしまうかもしれませんので、話し方や声色に注意しましょう。
一方で、オンラインは目の動きや表情など、応募者の表情が伝わりにくいことも懸念点にあげられます。
応募者の緊張からくるものであれば、質問の意図をしっかりと説明したり、できるだけリラックスできるような雰囲気づくりをします。物理的な問題であれば、画面との距離や画面の明るさなどの調整してもらう指示出しをしてみましょう。
環境を整えておくこと
オンライン面接をスムーズに進行させるためには、事前にインターネット接続、カメラやマイクの確認をおこないましょう。
また、整った背景や照明にも気を配り、静かな個室を確保するなど、面接中にトラブルが起きないように環境を整えておくことが大切です。
質問リストを用意しておくこと
対面面接と同様に、オンライン面接でも事前に質問リストを準備しておくとスムーズに進行できます。事前準備で面接の流れを整理しておくと、面接が効率的に進められます。質問リストをもとに、候補者のスキルや経験、適性を効果的に評価できるようにしましょう。
評価基準を決めておくこと
一貫した評価をおこなうために、オンライン面接でも評価基準を明確に定めておくことが重要です。どのスキルや経験を重視するのか、どのような回答が高評価になるのかを事前に決めておくことで、公平かつ客観的な評価が可能になります。
対面面接の確認リストを応用し、オンラインの評価も一律になるように準備しておくのがおすすめです。
面接時間を守ること
オンライン面接でも、面接時間を守ることは重要です。
予定した時間内ですべての質問が終わるように進行を管理し、候補者にとってストレスの少ない面接体験を提供しましょう。時間を守ることで、候補者からの企業に対しての印象もよくなります。
すべての面接において気をつけること
面接では、時間内で自然な会話をしつつ、確実に必要な質問をすることが大切です。
とはいえ、話の流れで雑談をしたり、話の内容がそれることは悪いことではありません。
例えば、複数の応募者のヘアメイクとしての技術力や経験が僅差である場合、コミュニケーション能力で判断する可能性もあるでしょう。このような場合は、むしろ応募者の人間らしさを知るよい機会になりますが、時間に配慮しながら必要な項目の確認を忘れないようにすることが大切です。
特に複数の候補者がいる場合、面接時間を統一し、同じ質問をして判断材料とすることで、公平な評価がしやすくなります。限られた時間を有効に活用するため、面接前にしっかりと準備しましょう。
採用活動のポイント
採用活動において、人事は、応募者を見極めることや選考に関する対応を求められます。
特に選考結果の通知は重要な仕事のひとつですので、適切なタイミングと方法で通知をおこないましょう。
面接時に見極めたいポイントは以下の記事で解説しています。
→該当記事は現在準備中です。
選考結果の通知はいつからいつまで?
採用活動では、迅速に選考結果を連絡することが大切です。
特に、採用したいヘアメイクさんとご縁があった場合、良好な関係性を構築することに努めましょう。
そのために、まず気をつけるべきことは、合格者への連絡が遅れないようにすることです。
選考結果の連絡が遅いせいで、採用辞退されてしまうこともあります。選考結果は、面接後できるだけ早く、明確なタイミングと適切な連絡方法で通知しましょう。
また、残念ながら今回は採用に至らない応募者に対しても誠意ある対応が必要です。
それぞれ気をつけるべきポイントと、適切な連絡方法を解説していきます。
選考結果を通知するうえで気をつけること
選考結果の通知をするときは、合否にかかわらず、以下の4点に気をつけましょう。
スピーディーに通知する
優秀な人材を確保するには、迅速な対応が重要です。
求職者は、他社でも選考を受けていることが考えられるため、連絡が遅れると採用辞退につながるかもしれません。アクションの速さは企業への信頼にもつながりますので、できるだけ早く連絡するようにしましょう。
応募者の気持ちに寄り添う
合否の連絡を待つ求職者は、不安や緊張を感じています。
選考通知の来ない日が続くと、応募者は採用の可能性が低いと思ってしまうものです。応募者に不安を感じさせないために、通知の速い企業は即日連絡をし、次の選考や内定について連絡するところもあります。
応募者の気持ちに寄り添い、選考の合否にかかわらず、面接後3日~1週間以内に連絡をおこなえると理想的です。
通知内容を間違えないようにする
通知内容の伝達ミスを防ぐため、慎重に対応することが求められます。
特に、複数の応募者がいる場合は、選考結果・次回面接日・勤務開始日など、重要な日付や情報を正確に伝えることが重要です。
求人応募へのお礼を伝える
選考結果の通知時には、事務的になりすぎることなく、応募者への感謝の気持ちを伝えましょう。
応募者は、採否にかかわらず、自分の会社に興味を持ち、応募してくれた大切な人材です。今回は残念ながら不採用となった場合でも、また次の機会に応募してくれたり、取引先や顧客になる可能性もありますので、誠意のある対応を心がけましょう。
選考通過・採用通知の対応
応募者が選考に進んだ場合、そして、ご縁があって採用となった場合など、前向きな通知をするときは、以下に留意しましょう。
できるだけ早く連絡する
すでにご説明したとおり、選考に通過した場合や採用が決定した場合は、速やかに通知をおこなうことが重要です。
優れた人材は他社からも求められるため、早急な対応が求められます。応募者との良好な関係を維持するためにも、できるだけ早く連絡しましょう。
タイトルだけで用件を伝える
ビジネスにおいては、用件を簡潔に伝えることが大切です。
採用活動においても、相手にわかりやすく伝えることを意識しましょう。
特に郵送やメールでの通知の場合、「どの企業からの連絡か」「何のための連絡か」を明確にします。このように、複数の企業から連絡を受ける応募者に対して、内容を迅速に把握してもらうため、他の企業と混合しないようにするための工夫をしましょう。
「いつ」「どこで」「何をするか」を伝える
選考に通過した場合や採用になったときは、次のステップについての情報を具体的に伝えることが大切です。
次回の選考では、「いつ」「どこで」「何をするか」を明確にし、必要な持ち物や地図、緊急連絡先などもあわせて案内しましょう。これにより、応募者がスムーズに次のステップへ進めるようにします。
選考通過・採用通知を郵送でするメリットとデメリット
郵送での通知は、入社手続きに必要な書類など、こちらから渡さなければならないものを送れるのが大きなメリットです。
ただし、配送と到着までに時間がかかることに留意しなくてはなりません。
人材採用はスピードが重要なため、選考通過や採用などの前向きな連絡の場合は、郵送のみの通知をおこなうことは少ないといえるでしょう。郵送を使用する際は、まず電話で連絡し、必要事項を伝えてから、次回の選考案内や郵送物を送付する旨を伝えるのがおすすめです。
選考通過・採用通知をメールでするメリットとデメリット
いつでも送れて、すぐに連絡が取れるメールは、選考通過や採用通知を送る方法として非常に多くの企業で活用されています。
一方で、読まれたかどうかわからない点がデメリットとしてあげられるため、タイトなスケジュールの場合は、電話で連絡してからメールを送ると親切で確実です。
また、採用活動のメールには作法があり、件名や文章の書き方に注意が必要です。
メールのタイトルに会社名や選考結果に関する旨を記載するなど、応募者に要件がスムーズに伝わる工夫をしてみましょう。
選考通過・採用通知を電話でするメリットとデメリット
電話は、早急かつ確実に応募者に連絡できるのがメリットです。
選考が面接まで進んでいたり、前向きな連絡の場合は、電話で直接伝えると応募者も安心してくれることが多いでしょう。また、その後も選考が続く場合、応募者の電話の反応や応対も参考になるかもしれません。
ただし、電話は記録が残らないため、認識の違いや伝達ミスも起こり得ます。トラブルを防ぐためにも、電話連絡時はメールや郵送を併用するようにしましょう。
書類審査を通過した場合の通知例
タイトル:書類選考結果のご連絡
▢▢ ▢▢様
お世話になっております。
株式会社■■■の採用担当でございます。
この度は弊社の求人にご応募いただき、誠にありがとうございます。
書類審査の結果、次の面接選考に進んでいただきたく、書類選考通貨のご連絡をしました。次回選考の日時は以下の候補からお選びいただき、ご都合の良い日時をお知らせください。
もしもご都合が合わない場合は、候補日をご連絡いただけますと幸いです。
候補日
◯月◯日 ◯◯時◯◯分〜◯◯時◯◯分
◯月◯日 ◯◯時◯◯分〜◯◯時◯◯分
◯月◯日 ◯◯時◯◯分〜◯◯時◯◯分
次回選考では、対面にてお話を伺わせていただく予定です。
何卒よろしくお願い申し上げます。
株式会社■■■
人事担当■■
面接選考を通過した場合の通知見本
タイトル:選考結果のご連絡
▢▢ ▢▢様
お世話になっております。
株式会社■■■の採用担当でございます。
この度は弊社の面接選考にご参加いただき、誠にありがとうございました。
面接選考の結果、次の最終面接に進んでいただくことになりました。
次回選考の日時は以下の候補からお選びいただき、ご都合の良い日時をお知らせください。
もしもご都合が合わない場合は、候補日をご連絡いただけますと幸いです。
候補日
◯月◯日 ◯◯時◯◯分〜◯◯時◯◯分
◯月◯日 ◯◯時◯◯分〜◯◯時◯◯分
◯月◯日 ◯◯時◯◯分〜◯◯時◯◯分
次回選考では、現場のスタッフも面接に参加させていただく予定です。
何卒よろしくお願い申し上げます。
株式会社■■■
人事担当■■
採用が決定した場合の通知例
タイトル:選考結果のご連絡
▢▢ ▢▢様
お世話になっております。
株式会社■■■の採用担当でございます。
この度は、弊社のヘアメイクアップアーティストとして採用が決定いたしましたことをご連絡いたします。心よりお祝い申し上げます。
つきましては、以下の日程で入社手続きをおこないますので、ご都合の確認をお願い申し上げます。
日時:◯月◯日 ◯◯時◯◯分
場所:株式会社■■■
持ち物:身分証明書、必要書類一式
ご不明点がございましたら、ご遠慮なくお問い合わせください。
どうぞよろしくお願いいたします。
株式会社■■■
不採用通知の対応
採用活動では、採用決定の連絡だけでなく、不採用通知の対応も重要です。
残念ながら不採用となった場合にも、以下の3点に気をつけながら迅速かつ誠意を持って対応しましょう。
直接的な言い方は避ける
不採用の通知を出す場合、具体的な理由について触れる必要はありません。
直接的な表現は避け、「残念ながらご希望に添えず」や「今回は見合わせていただく」などの表現を使いましょう。
再度応募をしてほしい場合は伝えておく
採用活動は縁なので、企業や仕事内容に興味を持ってくれている人材は貴重です。
人数制限などの関係で、素敵な人材ながら今回は採用に至らなかったという応募者がいる場合は、次のタイミングで再度応募をしてほしい旨を伝えておきましょう。
この場合、今後の求人時に再度連絡する方法もありますが、その際は個人情報の取り扱いに注意し、連絡先の保管について確認を取ることが大切です。
また、状況によっては、今回不採用になった理由を伝えておくことも検討しましょう。
例えば、現場の経験数や技術の問題などであれば、応募者としても次回までに改善できるかもしれません。
応募書類を返送もしくは破棄する
個人情報は、厳重に取り扱うなどの注意が必要です。
不採用となった場合は、応募者が提出した履歴書やコンポジットなどの作品集が現物であれば返送し、データであれば破棄するなど、適切な処理をおこないます。応募者に対して、書類の処理方法を明確に伝えることで、企業としての信頼も得られるでしょう。
不採用通知を郵送するメリットとデメリット
郵送のメリットは、応募書類を返却できることです。
不採用通知をおこなう場合、応募者から預かっている履歴書などの応募書類と、書面での不採用通知書を同封しましょう。
履歴書やその他の応募書類は、個人情報漏洩防止のためにも速やかに返却することが望ましいです。応募書類などを返却しない場合は、あらかじめ募集要項に記載しておきましょう。
また、郵送のデメリットは時間がかかることです。迅速な対応が求められる場合は別の方法と組み合わせて通知するようにしましょう。
不採用通知をメールでするメリットとデメリット
選考通過や採用通知同様、不採用通知をメールで送る企業は非常に多く、「〇〇様のご健勝とご活躍を心よりお祈り申し上げます」といった内容の一文が書かれることから「お祈りメール」と呼ばれることもあります。
いつでも送信でき、迅速に通知できるメールでの連絡ですが、相手に読まれたかどうか把握できないデメリットがあげられます。
不採用通知のメールは、件名や文章の書き方に注意が必要となりますので、フォーマットを作成しておくと便利です。
不採用通知を電話でするメリットとデメリット
電話は、早急かつ確実に応募者へ連絡できるのがメリットです。
不採用であることを伝えるため、気まずい気持ちになったり、相手のタイミングを考慮する必要があるものの、直接電話で伝えることで、企業としての誠意を感じてもらえるかもしれません。
このとき、電話は記録が残らないため、誤解やトラブルを防ぐために、電話連絡後にはメールでも内容を通知することが望ましいです。
また、郵送やメールはいわゆる「お祈り」の言葉を送れますが、電話の場合は対話となるため、不採用の理由を聞かれる可能性もあります。きちんと返答できるようにして起きましょう。
不採用通知の見本
タイトル:選考結果のご連絡
▢▢ ▢▢様
お世話になっております。
株式会社■■■の採用担当でございます。
この度は、弊社のヘアメイクアップアーティストの募集にご応募いただき、誠にありがとうございました。
慎重に選考をおこないました結果、誠に残念ながら今回はご希望に添えない結果となりました。ご期待に沿えず大変恐縮ではございますが、ご了承くださいますようお願い申し上げます。
尚、お預かりした応募書類を本状と同封してご返送させていただきましたのでご確認ください。
▢▢様のより一層のご健勝とご活躍を心よりお祈り申し上げます。
株式会社■■■
選考結果の連絡が遅れてしまうときはどうする?
企業として、選考結果を早く伝えようと努めても、様々な要因で連絡ができなかったり、遅くなってしまうことがあります。
どのようなケースがあるか事前に確認しておくことで回避できるトラブルもありますので、把握しておきましょう。
予想を上回る応募があったとき
予想を上回る応募があるのは喜ばしいことですが、書類選考や面接に時間がかかるため結果の通知が遅れます。応募者数に対する選考時間は余裕を持って設定しましょう。
社内の意見がまとまらないとき
採用活動を複数人で担当したり、応募者が複数人いた場合は、社内の意見がまとまらないこともあります。
「どんな人材が必要なのか」「どんなヘアメイクさんに働いてほしいのか」を明確にして、採用方針や評価軸を事前に明確にしておくことで、スムーズな意思決定が可能になります。
長期休暇を挟むスケジュールのとき
一般的に、採用通知は企業ごとの営業日とされていますが、選考のタイミングが夏休みや年末年始などの長期休暇に重なる場合、通知が遅れてしまいがちです。
例えば、面接後に長期休暇を挟み、そのあとの通知となると時間がかかりすぎてしまうため、応募者は不安なまま長い時間を過ごすことになったり、優秀な人材を逃す可能性もあります。
採用活動は、休暇前に結果を通知するか、休暇を避けたスケジュールで進行するようにしましょう。
合格者との連絡が取れないとき
採用通知を出した合格者と連絡が取れず、次のステップへ進めないことがあります。
例えば、採用通知を最初に出した人の回答により、そのあとの人たちへの通知内容が変動する場合も考えられるでしょう。
このような事態を防ぐためには、事前に連絡方法や通知時期の目安を伝え、迅速な対応を心がけることが大切です。
トライアル採用とは?試用期間との違い
採用方法のひとつ「トライアル採用」をご存知でしょうか?
トライアル採用は、通常1~3ヶ月間の一定期間、採用候補者を試用して能力や適性を確認する制度です。
この期間中、候補者は実際の業務を体験し、企業側は候補者の働きぶりやチームとの相性を評価します。そして、トライアル終了後、正式採用するかどうかを判断します。
トライアル採用のメリット
企業は実際の業務を通じて候補者の適性を見極められます。
また、候補者も職場環境や業務内容を体験できるため、納得したうえでの就職が可能となり、双方がミスマッチを防げます。
トライアル採用のデメリット
トライアル採用は短期間であるため、候補者の全体像を把握しきれない可能性があります。
また、候補者にとっては不安定な雇用形態であるため、大きな心理的負担がかかることも予想されます。
トライアル採用の実施方法
トライアル採用をおこなう際は、期間や条件を明確にし、事前に候補者と合意することが重要です。トライアル期間終了時には評価基準に基づき、正式採用の可否を決定し、通知しましょう。
また、トライアル採用は、よく「試用期間」と間違われることがあります。このふたつの違いは以下のとおりとなりますので、確認しておきましょう。
【トライアル採用と試用期間の違い】
| 雇用条件 | 期間 | 管理者 | 助成金の有無 | 雇用継続義務 |
| トライアル採用 | 原則3ヶ月 | 厚生労働省 | 有 (トライアル雇用助成金) | ・トライアル採用期間が終了したときに、雇用継続の有無を判断する・雇用を継続しない場合、特に手続きをせずに「解雇」扱いとなる |
| 試用期間 | 企業ごとに自由 | 企業 | 無 | ・本採用することが前提 ・解雇する場合は、通常の解雇時と同様の手続きが必要となる |
採用全般に関して注意すること
厚生労働省のホームページでは、各事業主に対して、公平な採用活動が求められています。
公平な採用活動は、応募者の基本的人権を尊重し、応募者の潜在的な可能性を見出す姿勢で、客観的に「公正な選考採用」をおこなうことを意味するため、様々な面に配慮が必要です。
例えば、出生・障害・マイノリティ・既往歴・難病などを理由にして、特定の人を排除することがあってはなりません。これらは偏見や差別につながる要因となるため、当事者が不当な扱いを受けることのないような環境づくりが求められます。詳しくみていきましょう。
参考:厚生労働省「公正な採用選考について」
公正な採用選考とは?
公正な採用選考は、応募者の適性や能力に関係のない事項で採否を決定しないことです。
例えば、家族や生活環境に関することなどを採用と関連づけてはいけません。そして、就職差別となり得るため、適性や能力に関係のない事項を応募用紙に記入させたり、面接で質問したりすることはNGです。
また、個人情報保護の観点からも、社会的差別の原因となるおそれのある個人情報などを「公共職業安定所等」「職業紹介事業者等」「労働者の募集をおこなう者」が面接や選考時に収集することは原則として認められていません。※
適性や能力に関連する質問や評価のみをおこなえるよう、配慮した質問リストを準備しておきましょう。
採用選考時に配慮すべき事項
採用選考時には、就職差別につながる可能性がある事項に配慮する必要があります。
これには、「本人に責任のない事項の把握」「本来自由であるべき事項(思想や信条にかかわること)の把握」「採用選考の方法」が含まれます。求職者の適性と能力に関係のない事項を応募用紙等に記載させたり、面接で尋ねたりしないようにしましょう。
以下を参考に、各項目について確認し、適正な採用選考をおこないましょう。
本人に責任のない事項の把握
求人に関係ない書類の提出要請
「戸籍謄(抄)本」や本籍が記載された「住民票(写し)」など、本籍・出生地に関すること
家族に関すること
職業・構成・健康・病歴・地位・学歴・収入・資産についてなど、身元調査、身辺調査などをおこなうこと
住宅状況に関すること
住宅の種類・家の間取り・近隣の施設についてなど
生活環境や家庭環境などに関することなど
現住所の略図等を提出させること
心身の状態を無理に把握しようとすること
まだ採用が決定していない選考段階で、合理的ではなく、客観的に必要性が認められない健康診断を実施すること
本来自由であるべき事項
日本国憲法第13条では「すべて国民は、個人として尊重される」と定められており、第19条では「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」とされています。そのため、採用選考において思想や信条に関する質問や情報収集は避けましょう。
具体的には、宗教・支持政党・人生観・尊敬する人物・思想・労働組合の加入状況などがあげられ、購読している新聞や雑誌などについて尋ねることも避ける対象とされています。
参考:衆議院「日本国憲法」
注意点
- 宗教や支持政党に関すること
- 人生観・生活信条・思想・マイノリティに関することなど
- 尊敬する人物に関することなど
- 労働組合への加入状況や活動歴など
- 学生運動などの社会運動に関することなど
- 購読している新聞・雑誌・愛読書などに関することなど
参考:厚生労働省「(3)採用選考時に配慮すべき事項」
質問について
面接時の質問には、企業として「したほうがよい質問」「してはいけない質問」と、応募者から受ける「逆質問」があります。
企業や仕事内容により質問は変わってきますが、まずは選考のベースとなり得るスタンダードな質問について確認しておきましょう。
「したほうがよい質問」とは?
各種選考は、企業にとっても応募者にとっても、入社後のミスマッチを防ぐために大切なステップとなります。以下の内容は、選考時点で確認しておくと安心です。
福利厚生・社内規定・ルールについて
いずれかの面接の中で、福利厚生・社内規定・ルールについて確認しておきましょう。
一般的に、求人情報に記載してある項目となりますが、それでも書ききれないことや詳しい説明が必要になるものもあるため、口頭で確認することが大切です。
福利厚生の充実は、働きやすいと感じてもらえるアピールポイントにもなります。
反対に、福利厚生に満足できていない場合は離職することになったり、認識のズレが生じていた場合、最悪トラブルにつながるケースもあるため、入社前にクリアにしておくことをおすすめします。
特に、企業独自の休暇やサービスについては、口頭で説明し、不明瞭な点がないかを確認したほうがよいかもしれません。
ヘアメイクは、クライアントや現場にあわせて稼働時間が変動することもあります。
社内規定やルールの説明にもかかわる部分となりますが、定休日や就業時間が不定期な場合は、その旨を伝え、対応できるかを確認したり、第級の取り方などを明確にしておきましょう。
「逆質問」にも対応すること
面接は、応募者と対面で会える貴重な機会となります。
このとき、応募者からの「逆質問」にも対応することが大切です。
こちらからの質問や、自社のことを説明するばかりではなく、「何か質問はありますか?」と尋ねるようにしましょう。
「してはいけない質問」がある?
先述したとおり、選考において、企業の採用担当者や面接官が聞いてはいけないことがあります。
特に、先述した「本人に責任のない事項の把握」にかかわる質問をしないように気をつけましょう。
【質問一例】
- 本籍や出身国などに関する質問
- 住居とその環境などに関する質問
- 家族構成や家族の職業・地位・収入などに関する質問
- 資産に関する質問
- 思想、信条、宗教、尊敬する人物、支持政党に関する質問
- 男女雇用機会均等法に抵触する質問
- 就職差別につながるおそれのある不適切な質問事例
詳しくは以下のサイトをご確認ください。
参考:厚生労働省「就職差別につながるおそれのある不適切な質問の例」
活躍してくれるヘアメイクさんを採用するためには
雇い主として、ヘアメイクさんに求めることは「自身の技術とセンスを持って活躍してくれること」です。優秀なヘアメイクさんと出会うために、ここからご紹介する3つのポイントと7つの記事を参考にしてみてください。
求人媒体にこだわる
この記事でご説明したとおり、ヘアメイクさんを雇いたい場合、求人媒体の選定は重要です。「どんなヘアメイクさんを求めているか」に応じて、適切な求人媒体を選びましょう。

求人のタイミングはいつ?
この記事でもご紹介したとおり、採用活動には時間がかかります。
求人媒体の選定、面接、入社手続きに加え、戦力として稼働してもらうために研修が必要な場合も想定しておきましょう。
採用の流れ
採用活動をスムーズに進めるためには、事前に採用の流れを把握しておくことが重要です。トラブルを防ぐためにも役立ちます。
【採用までの流れ一例】
求人媒体を探す
↓
募集をかける
↓
書類審査をする
↓
面接をする
↓
採用通知を出す
↓
入社の手続き
求人を出すときに企業が考慮すること
ヘアメイクさんを雇用したいときには、以下の3つの注意点を考慮することが重要です。
採用活動や雇用関係を結ぶ前に確認しておきましょう。
自社のために:「どんな人材がほしいのか」を明確にする
まずは企業にとってほしい人材像を明確にしましょう。
例えば、正社員か業務委託か、未経験可か経験重視かを決めるなど、自社が求める人材を明確にすることで、書類審査や面接の選考がしやすくなります。ブレることなくきちんと求める人材を採用することで、現場の仕事がスムーズに進行できるでしょう。
以下の記事では、優秀なヘアメイクを確保するために、採用活動でどのような点に気をつければよいのか、採用のポイントと注意点を解説しています。
→優秀なヘアメイクを確保するために、採用活動でどのような点に気をつければよいか?採用のポイントと注意点は現在準備中です。
従業員のために:勤務条件を明示する
勤務条件は、労働者が就業先を決定する際に非常に重要です。
基本的な給与・勤務地・仕事内容などの条件を明確にし、求人募集時に明記することで、労使で共通の認識を持つことができ、入社後のトラブルや不満を防ぐことにつながるでしょう。
以下の記事では、従業員と自社のために、ヘアメイクさんを採用するときの考慮点や注意点を解説しています。
→従業員と自社のために。ヘアメイクさんを採用するときの考慮点と注意点とは?は現在準備中です。
従業員と自社のために:採用にかかる時間と、採用後の収入(費用)を明示する
新しい人材の採用には費用と時間がかかります。
採用活動前に、企業にかかる負担や支出を明確にし、経営に支障が出ないようにしましょう。例えば、従業員にとっての収入となる「従業員に支払う給与」と、会社が負担する「見えない費用」を明確にしておく必要があります。
以下の記事では、求人から採用までヘアメイクを採用するときの費用を徹底解説しています。
→求人から採用までヘアメイクを採用するときの費用を徹底解説!の記事は現在準備中です。
従業員と自社のために:受け入れ体制、働きやすい環境を整える
昨今、会社組織における福利厚生や技術手当、研修やハラスメント対策の体制を整え、充実させることが、一昔前に比べてより強く求められるようになってきました。
従業員にとって働きやすい環境を整え、せっかく採用した人材が離れないようにすることが大切です。現場の仕事が円滑に進むように、労働環境づくりに取り組みましょう。
以下の記事では、従業員からもクライアントからも“選ばれる”ためのポイントを解説しています。
→従業員からもクライアントからも“選ばれる”就業先になるためにの記事は現在準備中です。
対面ならではのメリットを活用しよう
採用活動は、開始前から入社後まで、一連の流れの計画を立てることが大切です。
利用する求人媒体は、新卒向け採用サイトや転職者向けの求人サイト、専門学校との連携など、多様なアプローチを取り入れ、幅広い候補者にリーチすることが重要になるでしょう。
そのうえで、書類選考や面接を活用して、スキルや経験だけでなく、コミュニケーション能力や適応力も評価して、自社にマッチするヘアメイクアップアーティストを決定していきましょう。


